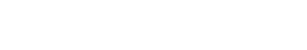2025 | © All rights reserved - Apex-Brasil
 1906年7月、笠戸丸(かさとまる)は東洋移民会社によりチャーターされ、ブラジルへの日本人移民輸送に使用された最初の汽船となりました。
1906年7月、笠戸丸(かさとまる)は東洋移民会社によりチャーターされ、ブラジルへの日本人移民輸送に使用された最初の汽船となりました。
現在、約250万人の日本人とその子孫がブラジルに住んでおり、これは日本国外で最も大きな日本人のコミュニティを形成しています。一方、約21万人のブラジル人が日本に住んでいます。
この日本人労働者たちのブラジルへの移民は、1908年6月にサントス港に最初の市民がカサトマル号に乗って到着したことで始まりました。その少し前の1895年、両国は友好、貿易、航海に関する条約を結び、今日に至る関係の始まりを記しました
それ以来、数多くの物語があります。移民した人々と、彼らを受け入れたブラジル社会にとって、前例のない経験が結びつきました。
ブラジルにおける日本人移民の存在は、身体的特徴や文化的特徴によって特徴づけられ、長年にわたり、さまざまな地域のブラジル社会に溶け込んでいきました。サンパウロ州は、ブラジルの首都を中心に130万人以上のニッケイ(日本国外で生まれた日本人の子孫)が住んでおり、次いでパラナ州、マットグロッソ・ド・スル州、パラ州、バイーア州などの他の州が続いています。
サンパウロに到着した日本人は、食料生産に従事し、次第に他の都市や州に移住しました。例として、1952年から1965年にかけて、パラ州は地元政府からの農業・森林活動に対するインセンティブにより日本人移民を受け入れ始めました。トメ・アス市は、ペッパー、クプアス、ピタヤ、メロン、スイカ、アサイーなどの果物やカカオの栽培に従事している移民とその子孫の大きなコミュニティを形成しています。
ブラジルに到着した最初の数年間、移民たちが直面した現実は全く未知のものでした。日本人移民たちは、徐々にブラジル文化を吸収しましたが、自分たちのアイデンティティと習慣を守ろうという決意を持っていました。
社会学者の斎藤弘が彼の著書『ブラジルの日本人:移動と定着の研究(1961年)』で述べているように、ブラジルは1925年に日本の移民政策を変え、過剰人口を受け入れる国から投資先の国へと変わったのです。このため、7年以上にわたり日本人のブラジルへの移住が続きましたが、1934年にブラジル政府が移民の入国を制限する法律を承認しました。
歴史を通じて、両国の相互の影響が明らかになり、さまざまな分野で協力が進みました。1960年代から1980年代にかけて、大企業が相互の支援で設立されました。例えば、ウジミナス製鉄所は、戦後初の日本からの大規模な投資で日本人の参加を得て設立されました。その他にも、セニブラ(ニッポン・ブラジレイラ製紙株式会社)やアルブラス(ブラジルの最大のアルミニウム生産者)などがあります。また、1958年にサンパウロに工場を設立したトヨタは、ブラジルでの最初の海外進出となりました。
両国間の歴史は広範で深いものです。日本とブラジルの間には大きな地理的な距離がありますが、日本文化はブラジルで高く評価されていると言えます。この二国間の交流をより良く理解するために、いくつかの関連性のある正当なデータを提供しているサイトがあります。いくつかご紹介します: